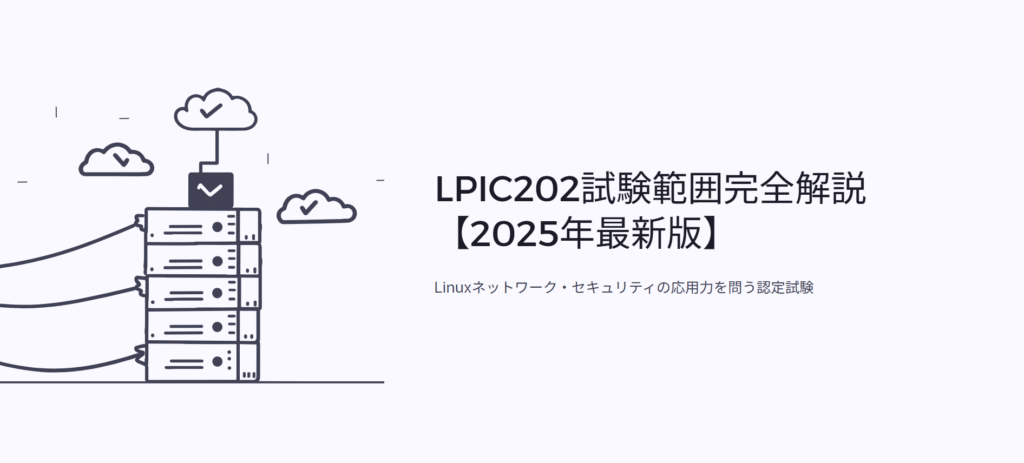最終更新日 2025年9月8日

- LPIC2おすすめ参考書ランキング
- 第1位 Linux教科書 LPICレベル2 Version4.5対応(あずき本)
- 第2位 Linux教科書 LPICレベル2 スピードマスター問題集 Version4.5対応
- 第3位 Ping-t(LPIC2対応オンライン問題集)
- 第4位 徹底攻略 LPIC Level2 問題集[Version4.5対応]
- 第5位 [試して理解]Linuxのしくみ ―実験と図解で学ぶOSの基礎知識
- 第6位 動かしながらゼロから学ぶ Linuxカーネルの教科書
- 第7位 DNSがよくわかる教科書
- 第8位 ITエンジニア1年生のためのまんがでわかるLinux シェルスクリプト応用&ネットワーク操作編
- 第9位 入門LDAP/OpenLDAP ディレクトリサービス導入・運用ガイド 第3版
- 第10位 学易(がくやす) – LPIC2対応 無料問題集サイト
LPIC2おすすめ参考書ランキング
LPIC2を受験する際にお勧めの参考書ランキングをまとめました。
エンジニア仲間に調査してランキングを整理したのでよかったら是非参考にしてみてください!
| 順位 | 商品画像 | 書籍名 | 値段 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ページ数 | 発売日 | 難易度 | 出版社 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Linux教科書 LPICレベル2 Version4.5対応 |
4,400円 | Amazon | 楽天 | Yahoo | 640 | 2017/5/11 | 中級 | 翔泳社 | LPI公式認定テキスト 試験範囲網羅 実践的 |
解説が丁寧 模擬試験付き 初学者でも対応 |
価格が高め 情報がやや古い 分厚くて重い |
| 2 |  |
Linux教科書 LPICレベル2 スピードマスター問題集 Version4.5対応 |
3,300円 | Amazon | 楽天 | Yahoo | 539 | 2017/10/30 | 中級 | 翔泳社 | 定番問題集 試験対応済 解説豊富 |
問題数が豊富 難問対応 本試験レベル |
厚くて携帯に不便 復習がしにくい 情報更新がない |
| 3 | Ping-t | 月額2,400円~ | – | – | – | – | – | 中級 | Ping-t | Web問題集 反復学習 模試機能あり |
利用が手軽 スマホ対応 学習効率が高い |
月額費用が必要 ネット環境が必要 無料ではない |
|
| 4 |  |
徹底攻略 LPIC Level2 問題集 [Version4.5対応] |
3960円 | Amazon | 楽天 | Yahoo | 122 | 2017/7/10 | 中級 | インプレス | 差分問題集 頻出問題に特化 応用力養成 |
価格が安い 解説が詳しい 要点整理されている |
問題数が少ない 基礎がやや薄い 内容がやや古い |
| 5 |  |
[試して理解]Linuxのしくみ 増補改訂版 |
3,520円 | Amazon | 楽天 | Yahoo | 336 | 2022/10/17 | 中級 | 技術評論社 | 図解多め 構造理解 最新OS対応 |
パフォーマンス理解 試験外も学べる 理解が深まる |
試験に直結しにくい 範囲が広すぎる 中級者以上向け |
| 6 |  |
動かしながらゼロから学ぶ Linuxカーネルの教科書 |
3,520円 | Amazon | 楽天 | Yahoo | 248 | 2024/7/18 | 中級 | 日経BP | カーネル特化 実験付き カーネル初心者向け |
体系的 演習しやすい 短時間学習OK |
試験範囲とずれる 一部高度 応用には不足 |
| 7 |  |
DNSがよくわかる教科書 | 2,508円 | Amazon | 楽天 | Yahoo | 340 | 2018/11/22 | 初級 | SBクリエイティブ | DNS集中 図が多い 初心者向け |
ネット系範囲を補強 設定例が豊富 内容が理解しやすい |
範囲が限定的 試験直接対策ではない 初級者向け |
| 8 |  |
まんがでわかる Linux シェルスクリプト応用& ネットワーク操作編 |
2,420円 | Amazon | 楽天 | Yahoo | 345 | 2022/6/18 | 初級 | 日経BP | まんが形式 ネット操作 入門に最適 |
親しみやすい 飽きにくい 初心者にやさしい |
試験に全対応ではない 応用不足 全範囲網羅せず |
| 9 |  |
入門LDAP/OpenLDAP 第3版 | 3,080円 | Amazon | 楽天 | Yahoo | 432 | 2017/11/14 | 上級 | 秀和システム | LDAP特化 実運用解説 導入事例あり |
現場知識につながる 中上級者向け 理解が深まる |
試験範囲外あり やや専門的 初学者には難しい |
| 10 | 学易 | 無料 | – | – | – | – | – | 中級 | 有志サイト | 無料Web問題集 厳選問題 わかりやすいUI |
コストゼロ 直感操作可能 時間効率が良い |
解説が少なめ 問題数が限られる 基礎のみ対応 |
LPIC2とは何かについては以下の記事で紹介しているのでよかったら見てみてください!
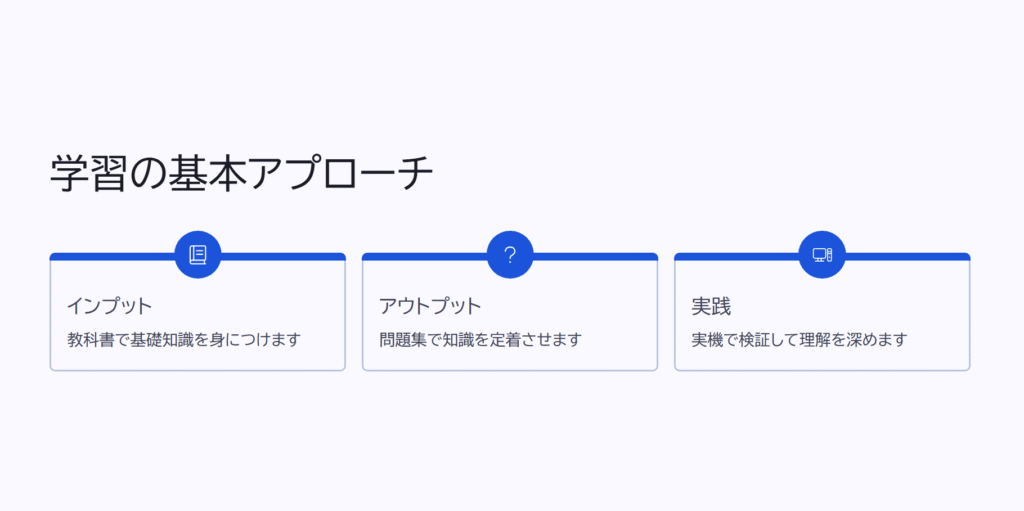
第1位 Linux教科書 LPICレベル2 Version4.5対応(あずき本)
「LPIC2対策本の決定版」として定番の参考書です。
茶色い表紙から通称「あずき本」とも呼ばれ、私もLPIC2学習の中心教材として使用しました。LPI公式認定テキストだけあって試験範囲を網羅しており、各章末には練習問題、巻末には201試験・202試験それぞれの模擬試験も付いています。Linux実習用の仮想マシン環境もダウンロード提供されており、実際にコマンドを動かしながら学べるのも魅力です。
初めてLPIC2を勉強する方は、まずこの一冊で基礎知識のインプットから問題演習まで一通り完結できます。私もレベル1の知識しかなかった頃、本書を読み込みながら重要ポイントを整理しました。内容はかなり詳細ですが、要所に図表や例が挙げられており理解を助けてくれます。試験直前まで辞書代わりに参照することで知識を定着でき、結果的に合格につながりました。

先輩、この「あずき本」って本当にLPIC2対策に向いてるんですか?

うん、間違いなく向いてるよ。LPI公式認定のテキストだから、出題範囲をしっかり網羅してるし、模擬試験もついてて、実力チェックにも使える。俺もこれを中心に合格までいったから安心して使っていいよ。
- メリット
試験範囲を漏れなくカバーしており、これ一冊でLPIC2の出題分野を網羅できます。解説も丁寧で詳しく、公式に準拠した信頼感があります。模擬試験や練習問題で実力チェックも可能です。 - デメリット
定価が約4千円台と少し高めですが、その分情報量が多く充実しています。また内容が専門的でボリュームも多いため、初心者には一読して全て理解するのは容易ではありません。難しい部分は飛ばして、後から何度も読み返す使い方がおすすめです。
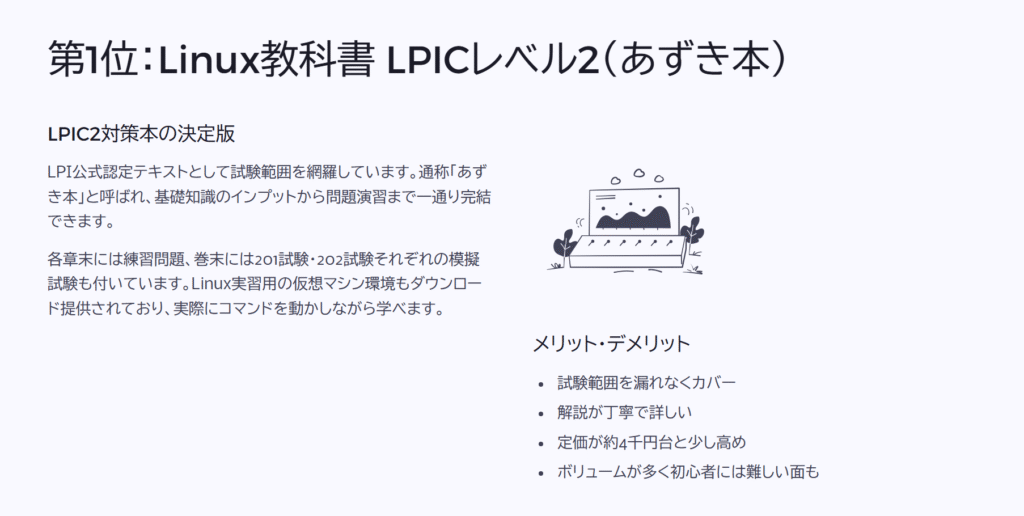
第2位 Linux教科書 LPICレベル2 スピードマスター問題集 Version4.5対応
LPIC2受験者なら必ず名前が挙がる定番の問題集がこちらです。
いわゆる「白本」とも呼ばれ、私もLPIC1に続いてLPIC2でも本書をメインの問題演習に使いました。LPI公式認定教材であり、Ver4.5対応の最新試験範囲に沿った問題を合計496問収録しています。各問題に対する解説が非常に充実しており、設定例のコマンドや図表も交えて丁寧に説明してくれるため、疑問点をその場で解消しながら進められました。
実際に本番試験を受けて感じたのは、本書から類題が多く出題されていたことです。
スピードマスター問題集の問題を繰り返し解いて理解を深めれば、合格ラインに必要な実力が身につきます。私も試験直前までこの白本を3周ほど解き直し、間違えた箇所は付箋を貼って重点復習しました。ただし536ページとかなり分厚いため、通勤時間などに持ち歩くのは大変です。その場合は後述のWeb問題集サービスと併用し、隙間時間はスマホで問題演習すると効率的でした。

この本は問題だけじゃなくて、解説もしっかりしてるんですか?

めちゃくちゃ丁寧。設定例のコマンドとか、図解まで入ってて理解が深まりやすい。疑問に思ったことも、その場でだいたい解決できるレベルだよ。
- メリット
LPIC2対策問題集の中で最もポピュラーで信頼できる一冊です。問題数が豊富で解説も詳細なため、弱点分野の補強や知識の再確認に最適です。公式の範囲に準拠している安心感もあります。 - デメリット
本の厚みと重量があるため、持ち運びやすさには欠けます。長時間机に向かえる環境で腰を据えて取り組む必要があります。また問題と解説が詳しい分、初見では理解に時間がかかることもありますが、繰り返し解けば自然と身についてくるでしょう。
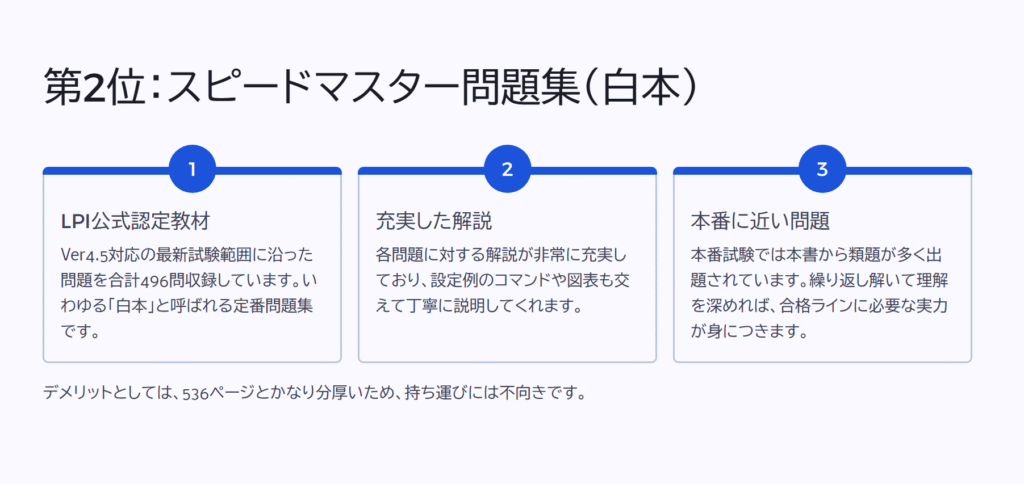
第3位 Ping-t(LPIC2対応オンライン問題集)
IT資格受験者にはおなじみのWeb問題集サイト「Ping-t」は、LPIC2対策でも非常に効果的でした。私が感じた最大の利点は、場所や時間を選ばずスマホで問題演習ができることです。
仕事の休憩中や通勤電車の中でも手軽に問題練習できたので、忙しい社会人学習者には特におすすめします。
Ping-tにはLPICレベル2向けに、201試験が約680問・202試験が約730問もの膨大な問題が収録されています。実際に解いてみると、本番試験と似た形式・難易度の問題が多く含まれており、出題傾向の把握に役立ちました。解説もスクリーンショットや図を交えて丁寧に書かれているので、参考書で曖昧だった部分もPing-tの解説で理解が深まることがありました。また利用者同士のQ&Aフォーラムがあり、分からない問題は質問して他の有資格者から回答をもらえる点も心強かったです。
私の場合、Ping-tを有料会員(月額課金)で2ヶ月利用して集中的に問題を解き込みました。
結果的に本番ではPing-tで見かけた問題が多数登場し、スムーズに回答できました。問題演習量を確保する意味でも、書籍の問題集に加えてPing-tを併用することを強くおすすめします。

本の解説よりPing-tのほうがわかりやすいですか?

場合によるけど、Ping-tの解説には図とかスクリーンショットもあって、参考書で曖昧だった部分がクリアになることもある。使い分けがおすすめ。
- メリット
Web上で提供される定番のオンライン問題集であり、約1400問という圧倒的な問題数を誇ります。いつでもどこでも学習でき、模擬試験モードで実力診断もできます。解説やフォーラム通じて疑問も解消しやすく、合格者の体験談など情報も豊富です。 - デメリット
LPICレベル2の問題は有料会員にならないと全て解けないため、月額利用料(1ヶ月あたり約2,400円)がかかります。ただし短期間で集中して使えばコストパフォーマンスは高く、LPIC3など上位資格を目指す場合にも継続利用できるので、必要経費と割り切っても良いでしょう。
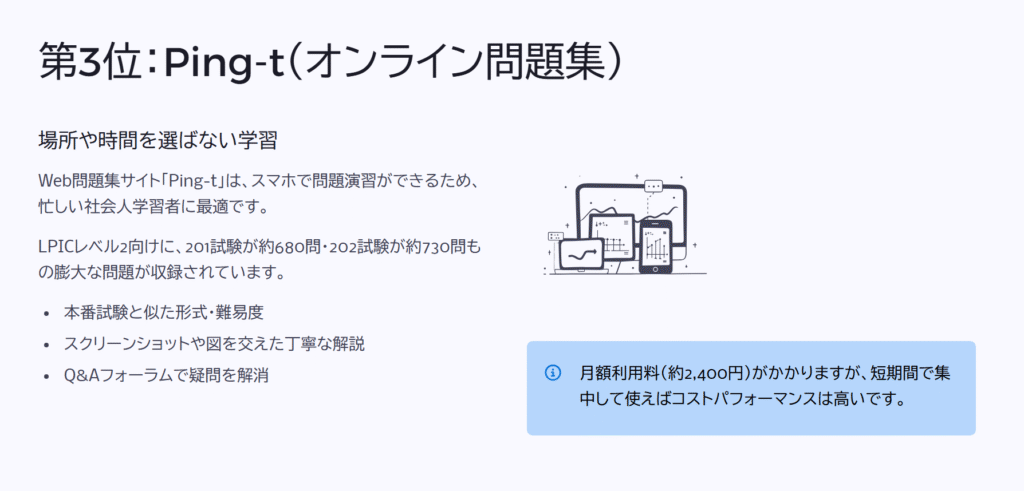
第4位 徹底攻略 LPIC Level2 問題集[Version4.5対応]
「徹底攻略」シリーズから出版されているLPIC2対応の問題集です。
こちらはVersion4.0用の問題集に対して、新試験範囲Ver4.5で追加・変更された内容を補う「差分対応」の問題集となっています。私はまず白本(スピードマスター)で一通り学習した後、余裕があれば2冊目の問題集として本書にも取り組みました。収録問題数自体はそれほど多くありませんが、その分解説が非常に詳しく初心者にも分かりやすいと評判です。
実際、本書にはLPIC201・202それぞれの模擬問題が1回分ずつと、Ver4.5で新たに追加されたトピックに関する演習問題が収録されています。白本で理解が曖昧だった領域も、本書の解説を読むことで「あ、こういうことだったのか」と腹落ちする場面が多々ありました。
例えばsystemd周りの設定やDocker関連の新出項目など、最新技術要素も丁寧にフォローされていた印象です。問題の傾向も白本とは若干異なるので、2冊目として解けば知識の漏れを補完できます。

先輩、「徹底攻略」の問題集って白本とはどう違うんですか?

一言でいうと“差分対応”。白本で一通り学んだあとに使うと、Ver4.5の追加内容を補完できる構成になってる。systemdやDocker関連とかね。
- メリット
スピードマスターと並んで人気が高い問題集であり、解説の詳しさには定評があります。特に新試験範囲の追加トピックについてわかりやすくまとまっているため、白本でカバーしきれない部分の補強に最適です。違った視点の問題に触れることで知識がより定着します。 - デメリット
本書単体ではLPIC2の全範囲を網羅しているわけではなく、あくまで差分補助的な位置付けです。そのためこれ一冊で完結するのは難しく、基本的には他の教科書や問題集と併用する必要があります。またページ数も少なめなので演習量としては不足気味ですが、重要ポイントの確認用と割り切って利用すると良いでしょう。
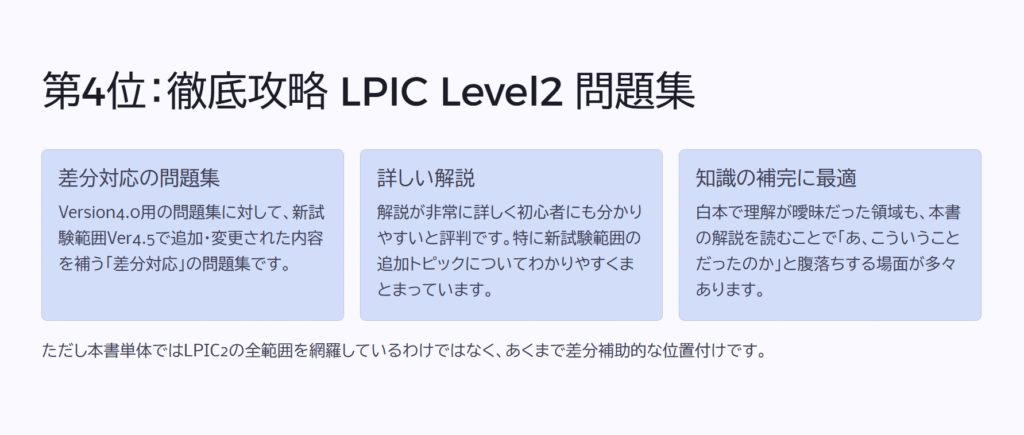
第5位 [試して理解]Linuxのしくみ ―実験と図解で学ぶOSの基礎知識
LPIC2学習中に私が「目からウロコが落ちた」一冊が、この『試して理解 Linuxのしくみ』です。
LPIC試験対策本ではありませんが、LinuxのOS内部の仕組み(カーネルやメモリ管理、プロセス、ファイルシステム、コンテナ技術など)をカラフルな図解と実験プログラムで分かりやすく解説しています。
特にLPIC201試験範囲にはLinuxの性能監視やチューニング、cgroupsといったOSの深い知識が問われる問題があり、私も当初これら抽象的な概念の理解に苦労していました。
しかし本書を読むことで、難解だったカーネルの動きやメモリの仕組みを具体的な実験結果とともに理解でき、体系的に腹落ちさせることができました。例えば、プロセススケジューラの章では実際に負荷をかけたときのCPU使用率の推移をグラフで示しながら、どのようにプロセスが切り替わっているかを説明してくれます。また仮想マシンやコンテナの章では、LPIC2では直接出題されない内容もありますが、現場で必要となる知識として興味深く読むことができました。
結果的にLinuxそのものへの理解が深まり、LPIC2の学習にも自信がつきました。

先輩、この「試して理解 Linuxのしくみ」ってLPIC2対策本じゃないんですよね?読む意味ありますか?

たしかに試験対策本じゃないけど、むしろOSの本質を理解するのに最適な一冊だよ。カーネルの仕組みとかメモリ管理とか、LPIC201で出る性能監視の理解にも役立つ。
- メリット
フルカラーの豊富な図やグラフを用いてLinux OSの動作原理を直感的に学べる良書です。特にLPIC201試験で比重の大きいパフォーマンスモニタリングやプロセス管理の知識を、実験を通して得られるため実践力が付きます。読後はLinuxシステム全体のイメージが掴め、応用的な問題にも対応しやすくなりました。 - デメリット
価格設定はやや高めですが、専門書として内容が充実しているため妥当とも言えます。またLPIC試験範囲以上のトピック(最新のコンテナ技術など)にも触れているため、試験対策という点では一部オーバースペックな情報も含まれます。ただし知的好奇心を刺激してくれる内容ばかりなので、「遠回りのようでいて本質的な理解が深まる一冊」として時間を割く価値は高いです。
![第5位:[試して理解]Linuxのしくみ
実験と図解で学ぶOSの基礎知識
LinuxのOS内部の仕組み(カーネルやメモリ管理、プロセス、ファイルシステム、コンテナ技術など)をカラフルな図解と実験プログラムで分かりやすく解説しています。
LPIC201試験範囲にはLinuxの性能監視やチューニング、cgroupsといったOSの深い知識が問われる問題があり、これらの理解に役立ちます。
フルカラーの豊富な図やグラフを用いてLinux OSの動作原理を直感的に学べる良書です。
価格設定はやや高めですが、専門書として内容が充実しているため妥当と言えます。](https://www.goritarou.com/wp-content/uploads/2025/07/image-19-1024x491.png)
第6位 動かしながらゼロから学ぶ Linuxカーネルの教科書
Linuxカーネルというと難解なイメージがありますが、本書は「手を動かしながら」カーネルの仕組みを学べる入門書です。
LPIC201試験でもLinuxカーネルの設定やコンパイル、チューニングに関する問題が出題されますが、単にテキストを読むだけでは理解が追いつかない部分もあります。私も当初カーネルパラメータの説明を読んでもピンと来ず苦労しました。そんなとき本書を参考に、実際に小さなCプログラムを書いてカーネルの動きを検証してみたり、カーネルソースをビルドする手順を試したりすることで、「なるほど、こういうことか!」と腑に落ちる経験を何度もしました。
本書は章ごとにテーマがあり、例えばプロセス管理やメモリ管理について、読者自身がコードを書いて挙動を観察する「実験」が用意されています。カーネルという抽象度の高い題材を、自分の目で確かめながら学べるので、難しい概念も記憶に残りやすいです。LPICの範囲としては直接は踏み込まない部分もありますが、カーネル周りの基礎を理解しておくと試験問題の選択肢にも迷いにくくなると感じました。私の場合、カーネルモジュールの扱いやメモリフットプリントの考察など、本書で得た知識がLPIC2の応用問題で役立ちました。

先輩、この「カーネルの教科書」ってLPIC2に直接関係あるんですか?

直接ではない部分もあるけど、LPIC201で出るカーネル設定やチューニングの理解を深めるのにめちゃくちゃ役立つよ。特に抽象的な設定値の意味が腑に落ちるようになる。小さなCプログラムを書いたり、カーネルソースをビルドしたりして、実際に挙動を観察する「実験形式」になってるのが特徴。読むだけより理解が深まるよ。
- メリット
Linuxカーネルの動きを実践的に体験しながら学べるユニークな教材です。難解なカーネル内部の仕組みも、自ら動かしてみることで基礎から理解できます。LPIC2の学習者にとってはカーネル設定項目など背景知識が深まり、単なる暗記ではなく納得して知識を習得できる点がメリットです。 - デメリット
取り扱う内容がカーネルに特化しているため、LPIC2試験範囲全般から見るとカバーする領域は限定的です。時間がない場合は本書まで手を広げる必要はないかもしれません。ただ、カーネル分野に不安がある方やより高みを目指したい方には強くおすすめできます。難易度自体は「ゼロから学ぶ」というタイトル通り平易に書かれていますが、実験には多少のプログラミング知識が必要なので、その点だけ注意が必要です。
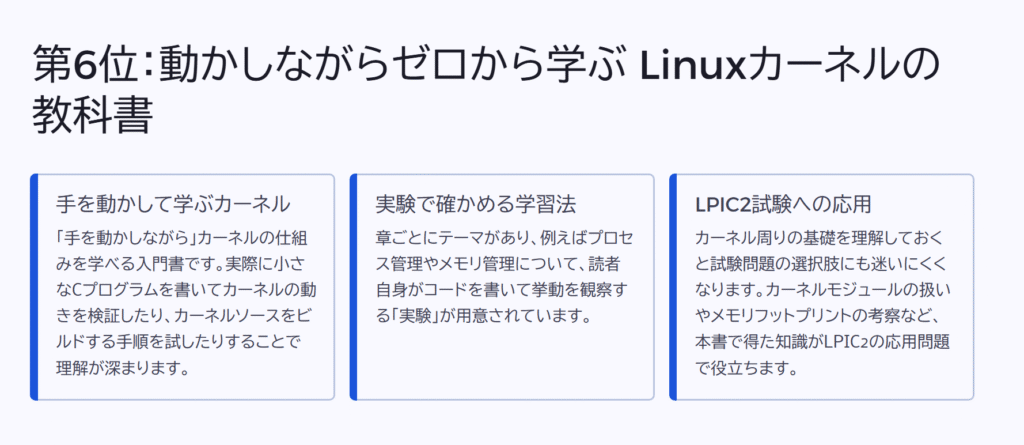
第7位 DNSがよくわかる教科書
DNSサーバについて体系立てて学べると評判なのが、JPRS(日本レジストリサービス)の技術者が執筆した本書です。LPIC202試験ではDNSに関する出題があり、私もBINDの設定やゾーンファイルの内容を理解するのに苦労していました。本書はDNSの基礎から運用ノウハウまで網羅した内容で、専門的なテーマを扱いながらも初心者にも優しい語り口で解説してくれます。
実際に読んでみると、ドメイン名の階層構造やDNSクエリの流れといった基本から丁寧に説明が始まり、リソースレコードの種類やBINDの設定方法、さらにはDNSSECや運用上の留意点まで順序立てて理解できます。私自身、LPICの勉強をするまでDNSを深く学ぶ機会がなかったのですが、本書で基礎を固めたおかげでゾーン転送の仕組みやレコードの意味をスムーズに理解できました。章末の練習問題も知識の確認に役立ち、学んだことが定着します。

先輩、この「DNSがよくわかる教科書」って、LPIC2の勉強にも使えるんですか?

めちゃくちゃ使えるよ。LPIC202で出てくるBINDの設定やゾーンファイルの理解にすごく役立つ。俺も最初DNSまわりが苦手だったけど、この本で基礎が固まった。
- メリット
DNSの全体像を体系的に習得できる良書です。初心者にとって分かりづらい概念も、用語解説から始まり図表を交えて噛み砕いているので頭に入りやすいです。LPIC2試験範囲のDNSトピックはこの一冊でほぼ網羅でき、実務に出た後も手元に置いて参照できる内容になっています。 - デメリット
本書はDNSに特化した教科書のため、LPIC2全般の勉強としてみると扱う範囲が限定的です。他のネットワークサービス(Webサーバやメールサーバなど)はカバーしていないので、あくまでもDNS分野の補強教材として位置付けると良いでしょう。また専門的な内容だけに、ボリュームがありじっくり腰を据えて読む必要がありますが、その過程で得た知識は試験のみならずエンジニアとしての強みになるはずです。
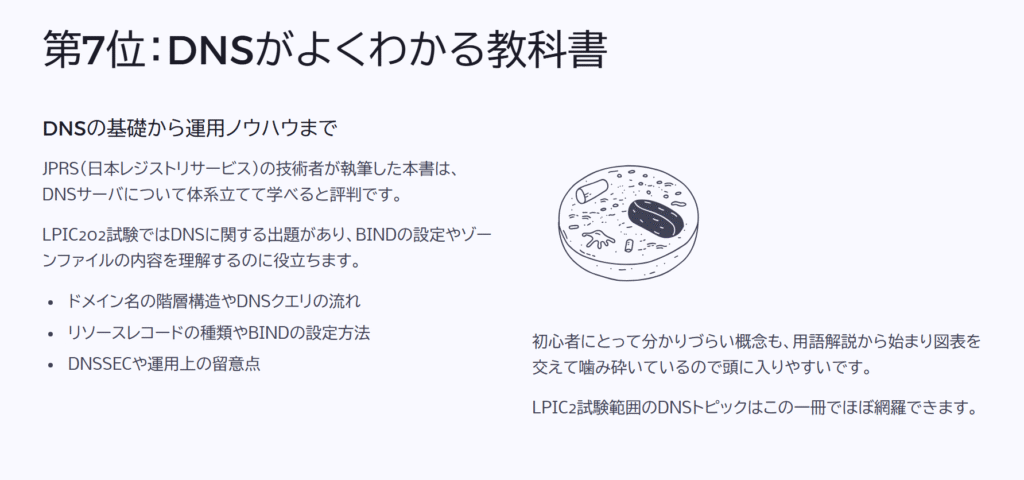
第8位 ITエンジニア1年生のためのまんがでわかるLinux シェルスクリプト応用&ネットワーク操作編
「文章だけの参考書は苦手…」という方には、こちらのマンガ形式で学べるLinux入門書がおすすめです。私もエンジニア駆け出しの頃に前作(基礎編)を読み、楽しくLinuxコマンドを覚えられた記憶があります。本書はその応用編として、シェルスクリプトの実用的なテクニックやネットワーク関連の操作方法を、物語仕立てで分かりやすく解説しています。
LPIC2ではシェルスクリプトやネットワークサービスの知識が求められますが、教科書的な文章だととっつきにくい内容も、マンガだとスイスイ頭に入ります。例えばgrepやfindコマンドを組み合わせた高度なファイル検索方法、iptablesによる簡単なファイアウォール設定、TCP/IPの基本的な動きなど、実務でも役立つ知識が漫画のストーリーに沿って自然と身につきます。私も本書を息抜きがてら読んで、堅苦しい参考書には載っていない現場のちょっとしたコツを得られました。試験勉強中に疲れたときは、このような読み物系の本で気分転換しつつ学習を進めるのも効果的です。

先輩、この「まんがでわかるLinux」って、LPIC2の勉強にも使えるんですか?なんか初心者向けって感じがして…。

たしかに入門向けだけど、シェルスクリプトやネットワーク操作の基本を実務視点で覚えるにはすごくいい本だよ。LPIC2の範囲にもけっこうかぶってる。
- メリット
マンガ形式で楽しく学べるので、Linuxの学習ハードルを下げてくれます。初心者でも理解しやすく、シェルスクリプトの活用術やネットワーク管理の基礎などをざっくり掴むのに最適です。文章だけでは頭に入りにくかった部分も、キャラクターの会話や図解で「そういうことか!」と納得できます。 - デメリット
あくまで入門・応用編という位置付けのため、LPIC2試験の全範囲を直接網羅するものではありません。この本だけで合格レベルに到達することは難しいですが、他の専門書と組み合わせることで理解が深まり学習効率が上がります。また楽しみながら読める反面、情報量は専門書より少なめなので、合格を目指すなら本書で興味を持ったテーマを別の参考書で掘り下げると良いでしょう。
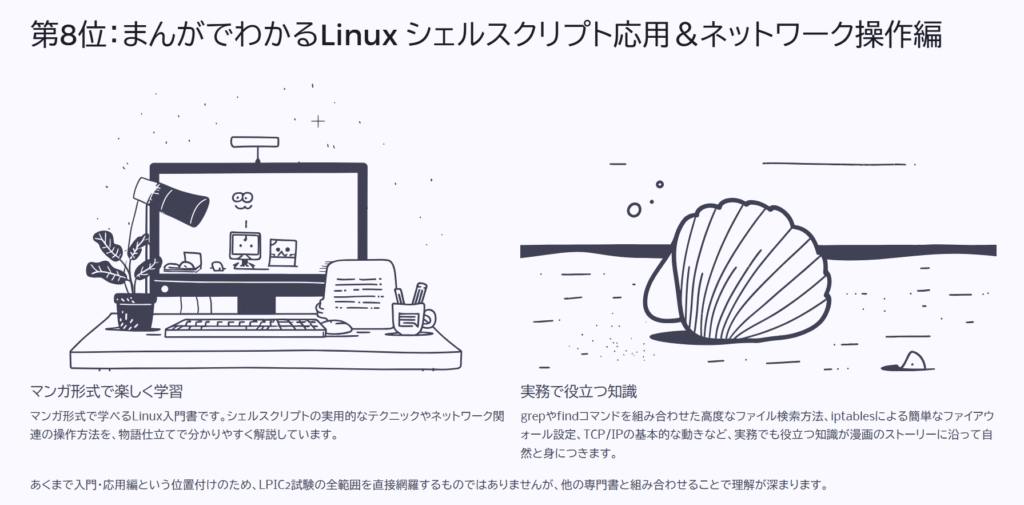
第9位 入門LDAP/OpenLDAP ディレクトリサービス導入・運用ガイド 第3版
LPIC2試験範囲には直接は登場しませんが、周辺知識として知っておくと役立つのがLDAP(ディレクトリサービス)です。特に企業システムではユーザ認証にLDAPを用いるケースも多く、LPICの上位試験や実務で必要になる場面があります。本書は国産のLDAP解説書として定評があり、OpenLDAPを用いたディレクトリサービスの構築・運用方法を基礎から詳しく説明しています。私もLPIC学習後半に読み進め、認証サービス全般の理解を深めるのに役立てました。
内容は、LDAPとは何かというプロトコルの仕組み説明から始まり、OpenLDAPサーバのインストール方法、基本的なエントリの追加・検索、アクセス制御の設定、さらに運用時のセキュリティやバックアップ方法まで網羅しています。正直、LPIC2の合格だけを考えれば必須ではありませんが、LPIC202試験範囲の「ネットワーククライアントの管理」や「セキュリティ」の分野で、LDAPの概念を理解していると選択肢の意図が読み取りやすくなることがあります。私自身、この本で学んだ認証周りの知識のおかげで、「LDAPを利用した中央認証」に関する設問にも落ち着いて対応できました。

先輩、この「入門LDAP/OpenLDAP」って、LPIC2対策に必要ですか?

合格だけが目的なら必須ではないよ。でもLDAPの基本を知っておくと、202試験のセキュリティ系やネットワーククライアントの問題が読みやすくなる。実務にもつながるし、知識の幅が広がる本だよ。
- メリット
LDAPの基礎から実践運用まで学べる貴重な一冊です。ディレクトリサービスという専門性の高い領域ですが、本書を通じて理解することでLinuxの認証機能(PAMやNSSとの連携)の背景知識が身に付きます。高度な内容まで扱っているため、エンジニアとしての知見を広げるのにも役立ち、LPIC2取得後さらに上位資格や現場スキルを伸ばしたい人には大きな財産になります。 - デメリット
専門性が高くボリュームもあるため、初心者には難しく感じるでしょう。LPIC2試験対策という観点では優先度は低めで、時間と興味に余裕がある方向けです。また2017年出版と少し古いため、最新のOpenLDAPバージョンとは設定ファイルの書式が変わっている部分もあります。それでもLDAPの根幹部分は変わらないので、基礎知識書として価値は色褪せません。
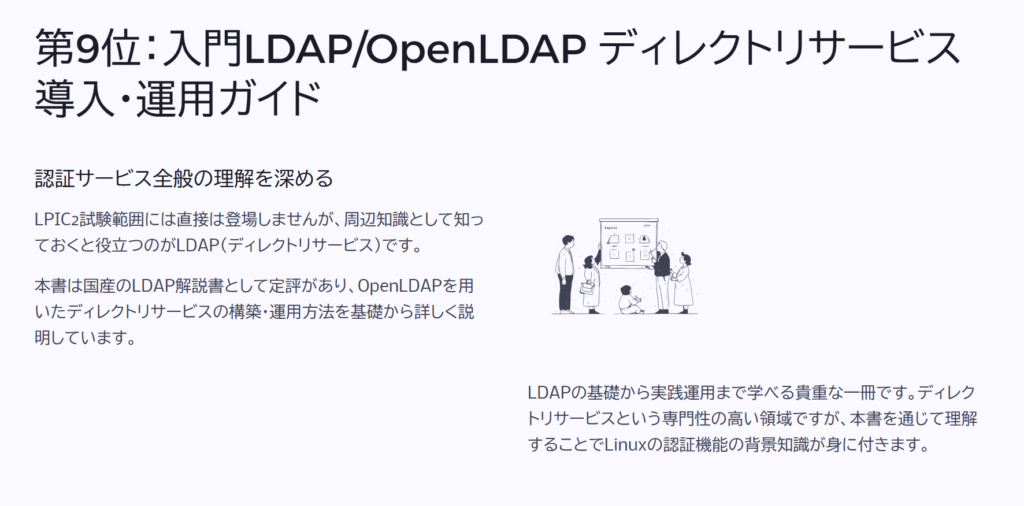
第10位 学易(がくやす) – LPIC2対応 無料問題集サイト
「学易」は、有志の方が運営しているインフラ系資格試験の問題集サイトです。LPICレベル2に関しては約50問程度の良質な練習問題が無料公開されています。問題数自体は多くありませんが、本番で問われやすいポイントを絞った問題が揃っており、短時間で効果的に知識をチェックできます。私も試験直前の力試しとして学易を活用しました。
会員登録(無料)をすれば誰でも利用可能で、Ping-tほど網羅的ではないものの厳選された良問が解けます。実際に解いてみると、「おっ」と思うようなひねりの利いた問題もあり、Ping-tや書籍にはなかった新鮮な切り口で理解度を測ることができました。特に私はメールサーバの問題で学易ならではの出題に遭遇し、自分の弱点に気付いて試験前日に復習できたのは幸運でした。また、学易ではLPICのお得な受験バウチャー(割引クーポン)の販売情報なども掲載されており、金銭面でも助けられました。

先輩、「学易」っていう無料の問題集サイトってどうなんですか?Ping-tとは違うんですよね?

うん、Ping-tほどの網羅性はないけど、学易は“厳選された良問”を短時間で解きたいときにピッタリだよ。問題数はLPIC2で50問くらいだけど、要点をしっかり押さえてる。
- メリット
完全無料で利用できるWeb問題集であり、スキマ時間にサクッと腕試しができます。厳選された50問ほどを解くことで、本番によく出るテーマの最終チェックに最適です。ユーザ登録すれば解答の保存やスコア管理もできるので、模試感覚で活用できます。 - デメリット
問題数が少ないため、これだけで十分な演習とは言えない点です。あくまで補助的な確認用ツールと割り切る必要があります。また提供されている解説は簡素なので、分からない部分は自分で調べる主体性も求められます。しかし無料で得られるメリットを考えれば、使わない手はないでしょう。
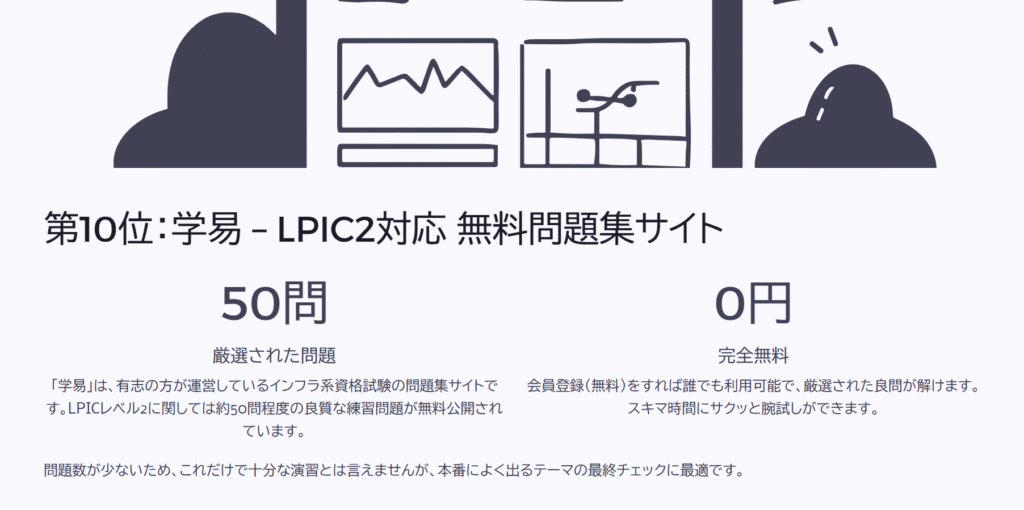
以上、LPICレベル2の合格を目指す上でおすすめの参考書・教材ランキング10選を紹介しました。私自身の体験を振り返ってみても、「インプット用の教科書」+「アウトプット用の問題集」+「Web教材の併用」が合格への王道パターンだと感じます。まずはランキング上位の教材を中心に据えて学習し、余裕があればその後に下位の教材で知識を補強すると良いでしょう。
最後に、LPIC2合格のためには継続的な学習と実機検証が大切です。
参考書を読んでコマンドや設定を学んだら、ぜひ実際のLinux環境で手を動かして確認してみてください。私も試験勉強中、自宅に立てた仮想Linuxサーバで何度も設定変更やサービス構築の練習をしました。その積み重ねが本番での自信につながります。
この記事が皆さんの学習のお役に立てば幸いです。LPICレベル2合格に向けて、頑張ってください!